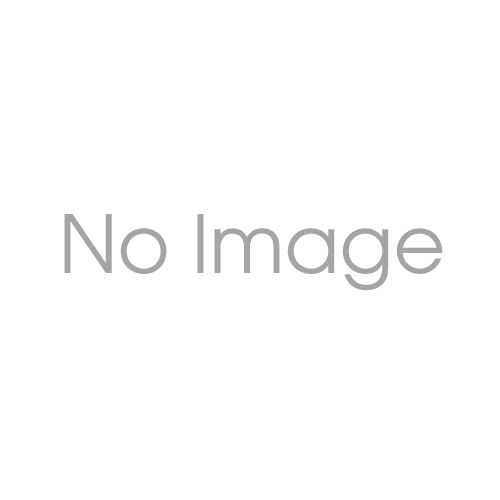記事公開日
最終更新日
お米 価格高騰!!食料の問題!!

最近、お米に関するニュースをたびたび目にします。2月7日の日本経済新聞では、「コメ民間輸入拡大(外食向け 兼松など2万トン超)」という記事が掲載されました。また、2月1日の日本経済新聞では、「備蓄米放出、流通不足時も(農水省、指針見直し了承)」という記事が掲載されました。どちらも昨夏から続くコメの値上がりに対応した内容です。
なんとなくお米については、行き当たりばったりの対策が否めないですね。渋沢栄一のように国家百年の計を考えての対応をとっているならよいですが、どうもしっくりといかないです。耕作放棄地が、2022年の農林水産省の発表で39.6万ヘクタール、2027年には42.3万ヘクタールになるとの予想まで出てます。このコメ不足の問題と、耕作放棄地、農家の後継者問題、食料の安定供給を結びつけて、解決策を見つけると未来に向けて明るい材料を提供できますね。
お米作りだけでなく、農業全般にDXを導入する傾向があります。まずは、DXを駆使して、人不足を解消し、効率的な農業を実施し、安全で安定した供給ができる農作物を増やしていくことが大事だと思います。また、今回の問題は、お米がどこにどのくらいどのような質のお米があるのかを、全国的に把握して各地の需要に応じて、品質の良い、安いお米を供給していくしくみができていない?か、機能していない?可能性があります。
食料を輸入するのは、反対はしませんが、何らかの原因でその輸入が止った場合のことも考えないといけません。どうもこの考えが欠けている感じです。ただでさえ円安で輸入品は高い筈ですが、それでもあえて買うというのは、量の問題ですかね。
個人消費も食料価格の高騰で、個人消費の重荷になっています。総務省の家計調査では、2024年の消費支出は、実質で前年比1.1パーセント減少しました。消費支出に占める食料の割合を示すエンゲル係数は、28.3パーセントと1981年以来の43年ぶりの高水準になりました。これに電気代・ガス代の高騰が加わり、個人消費は伸び悩んでいるのが実情です。
やはり、美味しい国産米を流通させること、耕作放棄地対策をすること、輸入が途絶えても、食料は自分の国の農産物で確保できることを軸に対応していく必要があります。最新の技術を使って、食料自給率100パーセント越えを目指す街づくりをすると面白いですね。その地区の耕作放棄地をなくし、後継者問題も解決し、食料も日々新鮮な食材が、地元の農家から手にはいる仕組みを作りましょう。日々の農業情報や観光客情報、イベント情報などをその地区の皆さんで共有すると面白いことが生まれそうな感じです。明るい街づくりになりそうな感じで、ワクワクしてきました。