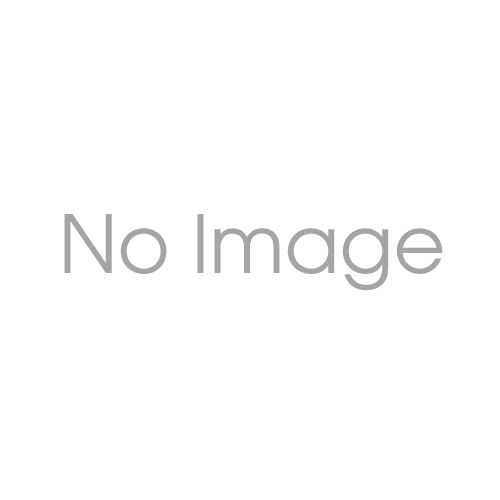記事公開日
最終更新日
戦略なき日本、水道が象徴!!

2025年2月16日の日本経済新聞で「戦略なき日本、水道が象徴」という記事が掲載され、八潮市の事故は、起こるべきして起きたという内容の記事がでてました。確かに水道問題は、今に始まった問題ではありません。水道管や下水道管は、高度成長期の人口が増えているときに埋設されている場合がほとんどです。人口が増えるばかり時代は、投資をすればどうにかなりました。日本の水需要のピークは、1998年くらいです。その後は洗濯槽等の性能が向上し、節水機能を使うことで水の使用量が減ってます。問題は、高度成長期に敷設された水道管や下水道管が腐食し、八潮市の様に漏水が発生していることです。今のところ、八潮市の下水道管や和歌山県の橋を渡る水道管の破裂以外は、あまり話題になってませんが、漏水件数は、年間2万件の発生件数になってます。これでも日本の場合は、現場力で押さえている状況で、少ない方だと思います。
特に問題なのは、人口が減っている地域の水道や下水道についてです。浜松市は日本で初めて、2018年4月に下水道をコンセッション方式で民営化し、上水道も計画していたことから住民から猛反発が起こりました。命の水を商売として使うのか??ということで、住民から猛烈なクレームがきました。水道行政は、はじめは各自治体ごとに水道局がつくられました。この流れの中で、財政基盤が弱い自治体は、水道局を運営することが厳しくなり、自治体が集まって広域で水道、下水道を運営するようになりました。運営は、纏めればよいのですが、水道管や下水道管の老朽化対策は、そのまま替えるしかないのが実情です。最近では、地震が起きて水道管や下水道管が壊れる危険性があるので、蛇腹型の水道管、下水道管を敷設する必要があります。意識して管を替えている自治体は良いですが、人もお金もない自治体は、手つかずになります。
驚いたのは、八潮市の下水道管の破損で影響を受けた住民の規模です。埼玉県北東部の120万人の住民が影響を受けました。防災の観点から考えると驚くべきことです。運営は広域でも良いですが、処理施設は狭い範囲で処理をしていく方式が適していると思います。当時は、大規模施設の方が経済的だったのでしょう。なんとなくこの仕組みをそのまま継承して、下水道管にセンサーを付けて、対応しようとしている感じです。もっと、狭い地域にして、電力も含めて地産地消のしくみは取れないでしょうか。考え方を変えないといけないと思います。
大規模施設の場合、住民の人口にあわせた水道施設にならないことです。狭い地域でコンパクトな対応施設なら、人口の増減にあわせて、施設の稼働を増やしたり、へらしたりできます。大規模の施設よりも、もっと融通が利くのでは??と思ってしまいます。コンパクトな施設がインターネットの網目の様に網羅されれば、水道や下水道は、一つ、2つの施設が壊れても、保持されると思います。我々としては、経済的な問題もあわせて考える必要がありますが、防災と防衛の観点からも考える問題だと思います。