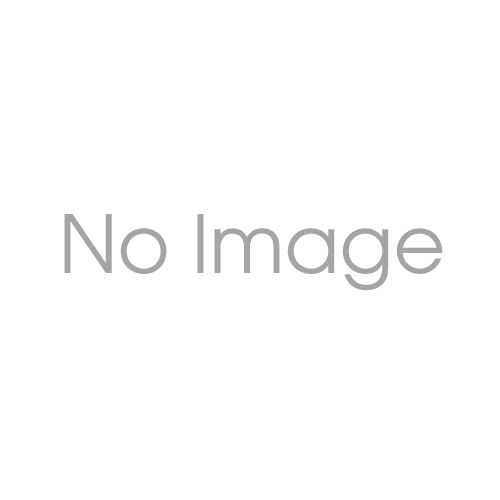記事公開日
最終更新日
災害ゴミの問題について!!

2025年3月9日の日本経済新聞に「災害ゴミ「置き場不足」半数」という記事が掲載されました。20政令市と東京23区で調査した結果です。災害ゴミの場合、収集などの初期対応が遅れれば衛星面の悪化や復興の停滞につながります。郊外まで宅地開発が進む都市部では空き地が少なく近隣住民の反発などで調整が難航する場合があります。東日本大震災の場合は、約3100万トンのがれきや津波堆積物が発生しました。自治体の処理能力をはるかにしのぎ、国の支援も得て、3年間かけて処理をしました。
災害ゴミの仮置き場は、土壌汚染の懸念から農地や学校の校庭などはふさわしくなく、車両の出入りがしやすい、郊外の空き地が候補としてあがります。ただ、そのような空き地は、仮設住宅の候補地にもなり得るため、自治体としては頭が痛いところです。
私は、熊本地震の時に福岡にいました。福岡の博多も揺れました。当時、日立グループに在籍しており、岡山から沖縄までの広範囲を営業責任エリアとして担当しました。妻の実家が熊本市内にあり、家具がひっくり返っていたので、休日に熊本の妻の実家に行き、倒れた家具を元に戻しいきました。その時の街の光景は、災害ゴミが一般のゴミ置き場から道路にはみ出して、積みあがってました。熊本は、地震は起きましたが、津波があったわけではありません。雨の災害があったわけでもありません。それでも災害ゴミが多くでることに驚きました。
災害ゴミの場合、短時間で処理しないといけないので、リサイクルとは無縁なのかと思いましたら、環境省のホームページを見たら、リサイクルをしているんですね。収集したゴミから金属を取り出して、再利用したり、コンクリートも破砕して、再利用をしてます。焼却灰も利用してます。このような動きが何故、話題になっていないのか??不思議です。岩手県では、350万トン、宮城県では947万トン、焼却灰の再生利用は、42万トンでした。かなりの再生率です。
災害ゴミの処理には、民間の力もうまく活用できないですかね。普段から、災害ゴミの様な種類のゴミが引っ越し等で出ると思います。この時のゴミを引き取って、リサイクルし、いざ、災害の時は、その機能を活かしつつ、規模を大きくして実施できたら、リサイクル品の販売ルートも確立できて、災害ゴミの収集スピードが上がるのでは??と思った次第です。また、各地でコンクリートの破砕ができる業者と提携し、災害時には破損した道路や破損した橋のコンクリートを現地で破砕して、そのまま復興に役立てることはできないですかね。。
能登半島の場合など、コンクリートやアスファルトを破砕して、新たに舗装しなおすことを実施した方が、復興が早いと思います。災害ゴミは、運ぶのが大変なので、現地処理が良いように思います。地産地消ですね。電気の調達、飲料水の調達、下水処理、食料の調達、家具等のリサイクル、耐震性の弱い、家の強化などを普段から地域で課題解決の議論をして、実施に移していると、レジリエンス力がついて、タフな地域が出来上がると思います。
普段から、災害に強い街づくりをいかにつくるのかを議論して、実行している土地が強いと思います。地域の皆さんと外部の人たちとの交流も必要ですね。お金も大事かもしれませんが、アイデアも大事だと思います。皆さん、災害に強い日本を作りましょう。