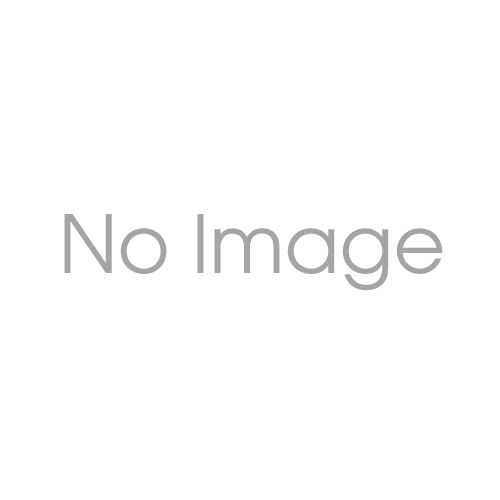記事公開日
最終更新日
「国産飼料の普及について」

2025年1月13日の日経新聞に「国産飼料の普及後押し」という題名の記事が記載されてました。日本の食料自給率は38パーセントですが、2023年度の飼料自給率は概算値で27パーセントです。記事では、この数値を少しでも改善しようと国産の飼料の普及に取り組んでいる内容が書かれてました。
そもそも、円安の関係もあり、輸入する飼料のトウモロコシなどの穀物の価格が高騰して、畜産農家の経営が苦しくなっている現状があります。この状況を改善するため、地域で支援して、国産飼料を作り、国内で自給自足できる仕組みを作る必要があります。価格高騰が原因ですが、その他の要因として、トウモロコシ等の穀物を燃料用に回していることもあります。要するに日本にくる穀物の量が少なくなって、価格が高くなっています。
日本の場合、島国なので、例えば、台湾と中国の関係で台湾周辺の海域で船舶が通行できなくなると、日本には、食料、飼料、石油、天然ガスなどが届かなくなり、苦しい状況に陥ることが想定されます。そのような状況にさせないためにも、まずは食料自給率と飼料自給率を上げておく必要があります。食料安全保障の課題です。
私は、この食料自給率と飼料自給率を向上させるために、耕作放棄地を活用できないかと考えてます。2022年に判明している耕作放棄地は、日本全国で農林水産省の発表では39.6万ヘクタールです。因みに東京ドームの広さは、4.7ヘクタールです。如何に巨大な耕作放棄地があることが分かります。ここに食用のお米と飼料用のお米をクさんの肥料で作れば、輸入が一時途絶えたとしても、日本に住んでいる人たちが、生き抜ける可能性が生まれます。農家の高齢化も問題ですが、嘆いていても解決しません。有志で農地を循環型社会の一部に取り入れていくしかないと思います。
農村が廃れて久しいですが、農地を復活させる意味は、食料の他にも意味があります。クマが市街地に入ってくるという現象も、森と人が生活する区域がわかりにくくなっているのが一つの要因です。クマ出没地域の耕作放棄地に手を入れることは、クマの生活圏を区分する意味でも重要です。その他、世界では淡水生物の4分の1が絶滅危惧種と言われてます。日本でも国内固有の淡水魚の4割が絶滅するのでは??と言われてます。これを改善するには、耕作放棄地を減らし、自然に近い形で農業をするのが良いと思ってます。河川の三面工事が一番の原因だと思いますが、私の小さい頃は、多くのカエルやタニシが田んぼにいました。昔の田んぼは、地球に優しかったのだと思います。生物がたくさん生息出来ました。
国産飼料や食料を作る上では、買ってくれる人たちがいないと、生産者の生活が成り立ちません。しっかりと理解者を増やし、必ず買ってくれる人たちを作り、食糧自給率の向上ができる体制を作っていく必要があります。私が、日立製作所に勤務していた時代に企業の融資の問題で日立系のクレジット会社と連携して提案したことがあります。その提案内容は、入り口から出口までをきっちりと定めた上で、上流の生産工程を強化するための融資をするというものです。下流では、その製品を買ってくれる業者をあらかじめ準備しておきます。この循環が出来れば、融資がうまくいくということでした。
脱炭素の時代なので、耕作放棄地で太陽光発電、風力発電と農業の共存についても追及していくと、もっと持続性ができてくると思います。エネルギーの自給自足も一つの解決すべき問題です。食料、飼料だけでなく、エネルギーが途絶えると、日本民族は窮地に追い込まれます。飲み水についても考えないといけません。
持続的な社会を作らないと、生きるのに厳しい時期が来ます。どうすれば解決するという明確な解はないですが、自分で、できることをひとつひとつ実施していくしかないと思ってます。北京で一匹の蝶々が羽をはばたかせると、ニューヨークで嵐になるという言葉があったと思います。一人の善意の努力が、世界を動かす。そんな世界ができると良いです。皆さん、明るい未来のために前進しましょう。